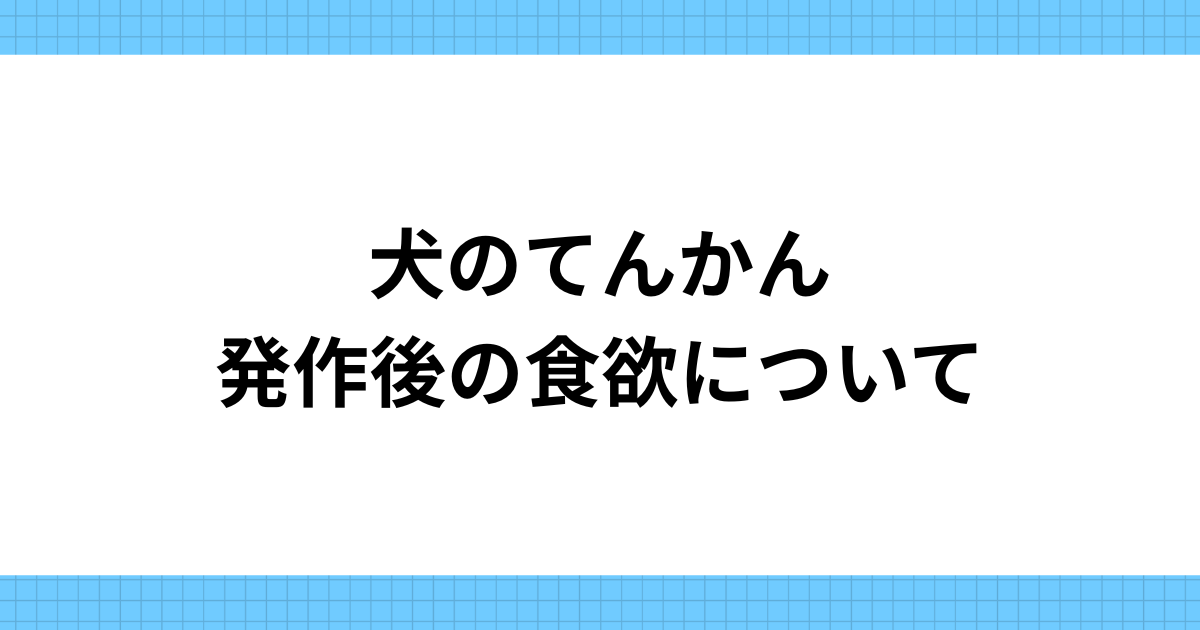犬のてんかん発作後、「ご飯を全く食べなくなった」「逆に食べたがって落ち着かない」など、食欲の変化に戸惑う飼い主さんは多いです。
発作後の体は大きなストレスを受けており、食欲が「落ちる子」「増す子」どちらの反応も見られます。
この記事では、獣医師の見解や一般的な傾向をもとに、それぞれの理由と対処法をまとめます。
発作後に食欲が変化するのはなぜ?
発作後の犬の体は、筋肉のけいれんや脳の興奮で多くのエネルギーを消耗しています。
そのため、犬によっては「疲れて食べたくない」子もいれば、「エネルギーを補いたい」と感じて食欲が増す子もいます。
主な原因は以下の通りです:
- 脳や体の疲労
- 薬の副作用(眠気・吐き気・だるさなど)
- 興奮状態が続いている
- 飼い主の不安が伝わる(ストレス性の反応)
食欲が落ちる子の特徴と対処法
発作後にぐったりして食べない場合、体の回復に時間が必要です。
対処法:
- 無理に食べさせず、安静を優先する
- 少し元気が出たタイミングで、ふやかしたフードやウェットタイプを与える
- 水分をしっかり確保する
- 24時間以上食べない場合は動物病院へ
💡発作後に「冷たい水」を嫌がる子もいます。常温の水に変えるだけで飲みやすくなることもあります。
食欲が増す子の特徴と対処法
一方で、発作後に落ち着かず「何か食べたい」「ソワソワして歩き回る」子もいます。
これは、発作の興奮状態や「体がエネルギーを欲している」サインのことも。
対処法:
- 一度にたくさん食べず、少量を数回に分けて与える
- 消化の良いフード(ふやかし・ウェット)を選ぶ
- 食後は静かな環境で休ませる
- 吐き戻しがある場合はすぐに獣医さんに相談
💡発作後に「食べて落ち着く」タイプの犬も少なくありません。
これは安心感や満足感を得ている証拠で、体と心の回復に役立つ場合もあります。
食欲の変化が続くときは要注意
数日続く場合や、いつもと違う様子(吐き気・下痢・再発作など)が見られるときは、
薬の副作用や他の病気が関係している可能性もあります。
様子がおかしいと感じたら、次の点を確認して獣医師に相談しましょう。
- 発作日記に「食欲・ご飯量・発作時間」などを記録しておく
- 発作の頻度や持続時間が増えていないかチェックする
- 元気や反応、歩き方にいつもと違いがないか見る
👉 数日たっても落ち着かない、または発作の間隔が短くなる場合は、薬の調整や追加検査が必要なこともあります。
早めに動物病院へ相談するのが安心です。
まとめ
- 発作後の犬は「食欲が落ちる」「増す」どちらの反応もあり得る
- 無理に食べさせたり制限したりせず、様子を見ながら調整する
- 食欲の変化は体調を知る大切なサイン
- 不安なときは早めに獣医に相談を
🔗我が家のゴールデン・ミニの場合(発作後に食欲が増すタイプ)もまた紹介します。
📚参考情報
- 日本動物病院協会(JAHA):「てんかんを持つ犬との暮らし方」
(https://www.jaha.or.jp/dogs/epilepsy) - MSDアニマルヘルス:「犬のてんかん発作について」
(https://www.msd-animal-health.jp/pethealth/dog-epilepsy) - Hill’s公式サイト:「てんかん発作を起こした犬のケア方法」
(https://www.hills.co.jp/dog-care/healthcare/epilepsy) - いぬのきもちWEB MAGAZINE:「犬のてんかんとは?症状と治療法」
(https://dog.benesse.ne.jp/withdog/content/?id=20126)