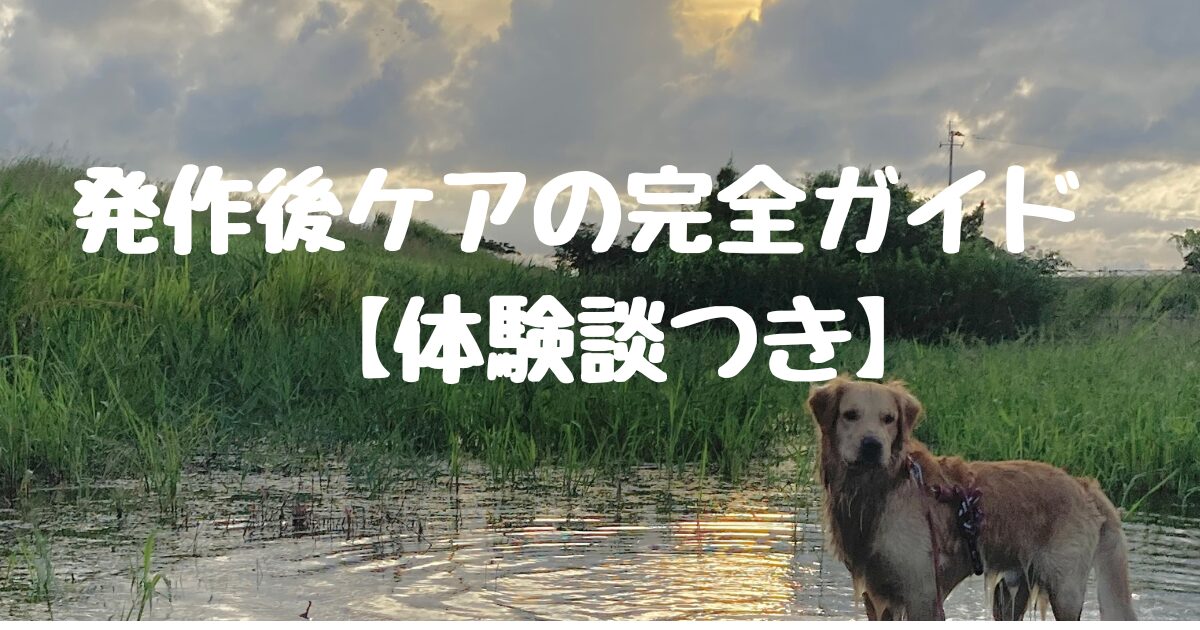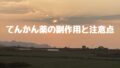はじめに
犬のてんかん発作は数分で自然に治まることが多いですが、その後は脳や体に大きな負担がかかります。ぐったりしたり、ふらついたり、意識がもうろうとする状態は数分から数時間続くこともあります。
発作後の過ごし方は、回復や次の発作予防にもつながる大切なポイントです。
この記事では、一般的な発作後ケア方法と、我が家の愛犬「ミニ」の場合の体験談をまとめてご紹介します。
1. 発作後すぐの対応(一般情報)
- すぐに起こさない ぐったりして眠ることがありますが自然な回復過程です。無理に起こさない。
- 呼吸・意識を確認 呼吸が止まっていないか、舌の色が紫になっていないかを見る。
- 静かな場所で安静に
発作直後は脳が混乱し、不安定な状態です。テレビや人の声など刺激を避け、暗めで静かな場所に移動させましょう。声かけや撫でる行為も最小限にし、そっと見守ります。 - 水や食事は様子を見てから
喉が渇いていても、ふらつきや意識が混乱している間は誤嚥の危険があります。立って歩ける、顔つきが普段に戻ったなど落ち着いてから、少量ずつ与えましょう。 - 病院に連絡すべきケース
- 発作が5分以上続く
- 数時間以内に複数回発作が起きる
- 意識が戻らない、呼吸がおかしい
- 初めての発作で原因不明の場合
発作後の観察ポイント(記録しておくと良い)
- 発作の開始と終了時刻。
- 発作の様子(体の動き、よだれ、排尿排便など)。
- 発作後の状態(ふらつき、ぼーっとしている、眠ってしまうなど)。
- 発作前の状況(興奮、食事、睡眠不足、体調不良など)。
👉 発作日記をつけておくと、獣医師が治療方針を立てる上でとても役立ちます。
2. 発作後数日〜日常生活での工夫
- しばらく安静を優先する 発作後は体力消耗が大きく、ぐったりしたり眠気が続くことがあります。無理に散歩や運動をさせず、自然に回復するまで休ませましょう。
- 刺激を避ける 大きな音、強い光、人混みなどは神経を刺激し、再発の引き金になることがあります。数日は静かな環境を心がけましょう。
- 歩き方や様子の観察 発作後にふらつきや方向感覚の乱れ(後遺症のように見える)が数時間〜数日続く場合があります。転倒の危険があるので、フローリングには滑り止めマットを敷くなど工夫を。
- 食事
一部では高脂質・低糖質の「ケトジェニック食」が有効とされていますが、導入は必ず獣医師に相談を。サプリメントも自己判断せずに。 - 睡眠
睡眠不足は発作の誘因になりやすいため、就寝時間を一定にし、静かな環境を整えます。 - ストレス管理
環境の急な変化(模様替え、大きな音、来客など)は避けましょう。留守番時間を短くする工夫も有効です。
3. 家の中の安全対策
- 滑り止めマットで転倒防止
- 階段や段差には柵を設置
- 夜間の発作に備えて常夜灯を点ける
- 家具の角にカバーを付ける
【体験談】ミニの場合の発作後ケア
我が家のゴールデンレトリバー「ミニ」(2歳)の場合をご紹介します。
- 発作後は目が見えづらく、壁や家具にぶつかるので下のものを片付ける
- 怖いのかソワソワして眠れないため、いつもの部屋に入れて寄り添う
- 睡眠不足や暑さが発作の誘因になりやすいので、徹底的に管理
- 発作後、ご飯を食べたがるので、与えると落ち着いてくれる
※これはあくまでミニの場合の例で、他の子にも当てはまるとは限りません。
「詳細」
発作後は視力が落ちるのか、下の物につまずいたり壁にぶつかったりすることがあります。そのため、水入れや餌皿、クッションなどを片付け、頭を打たないように落ち着くまでそばについて見守るようにしています。
一般的には「声かけや撫でる行為は最小限に」とされていますが、ミニの場合は発作後に不安になるのか、そばにいないと中々眠れません。そこで、落ち着いて眠りにつくまではいつもの部屋で寄り添うようにしています。その際も、過度に声をかけたり撫でたりはせず、安心できる距離感を保つように心がけています。
これまでの経験から、ミニは睡眠不足や暑さが発作の引き金になりやすいと感じています。そのため、日常生活の中でも特にこの2点には細心の注意を払っています。
また、最近気づいたことなのですが、ミニは小さい頃から興奮するとご飯を欲しがるタイプでした。発作後、なかなか落ち着いてくれない際に、ご飯の残りをバクバク食べていたのですが、なんと、そのあとはぐっすり寝てくれました。最近では、発作後少し時間を空けご飯を与えるようにすると、落ち着きが早いように感じています。
もちろん、この方法がすべての犬に当てはまるわけではありませんが、我が家の場合はこのように工夫しながら向き合っています。
まとめ
発作後は「静かに休ませ、安全を確保し、無理をさせない」ことが基本です。
ただし、犬のてんかんは原因や症状などと同様に、最適なケア方法もそれぞれのワンちゃんによって異なります。
一般的な情報をベースに、愛犬の様子や性格に合わせた工夫を少しずつ見つけていきましょう。