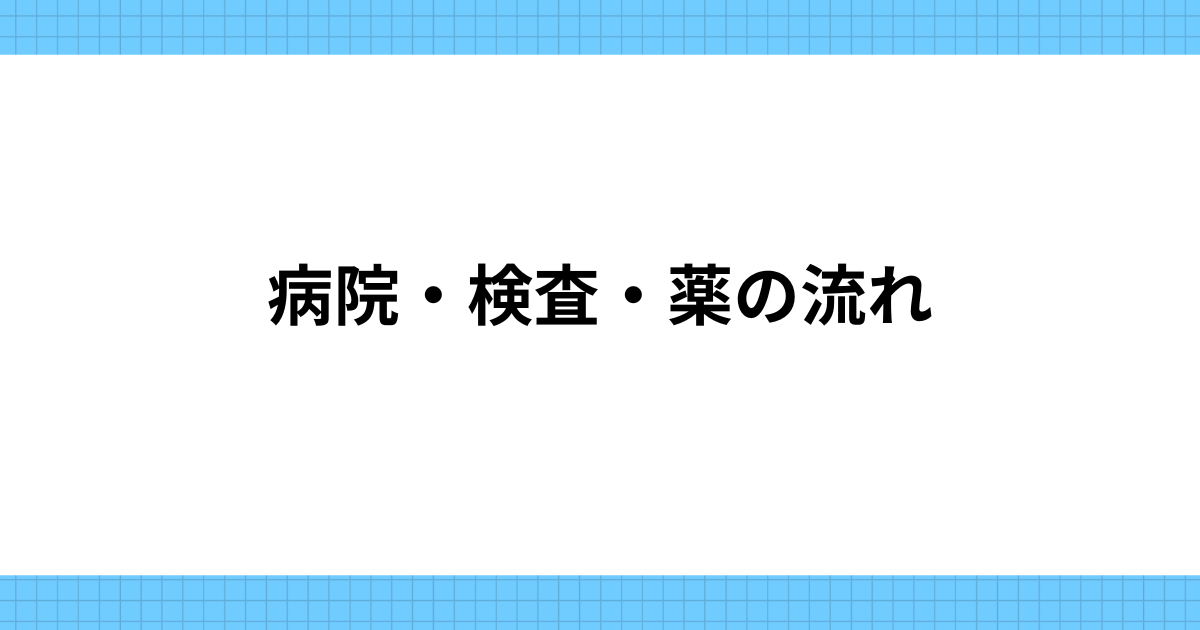犬がてんかんのような発作を起こした場合、多くの飼い主さんが「すぐに大きな検査をしたほうがいいの?」「薬はいつから始めるの?」と迷われると思います。ここでは、一般的な病院受診から検査、薬の流れを整理しました。
1.まずは動物病院での診察
発作が起きたら、まずかかりつけの動物病院へ相談します。
このとき、発作の様子を動画に撮って見せると診断の助けになります。
診察では次のような確認がされます。
- 発作の頻度、時間、様子
- 既往歴(過去の病気やケガ)
- 家族歴(遺伝性の可能性)
- 一般的な身体検査
ここで「てんかんの可能性があるか」「別の病気の可能性が高いか」が大まかに判断されます。
2.血液検査やレントゲンなどの一般検査
まず行われるのは、血液検査やレントゲン、超音波などの一般的な検査です。
これらは「てんかん以外の病気が原因で発作が出ていないか」を調べるために行われます。
例:
- 低血糖
- 肝臓や腎臓の病気
- 電解質異常
- 中毒
こうした病気が原因の場合は、てんかんの薬ではなく原因の治療が優先されます。
3.MRIやCTなどの高度検査について
一般検査では原因が分からない場合、「特発性てんかん(原因が特定できないタイプ)」の可能性が高くなります。
ここで選択肢に入るのが MRIやCTなどの高度画像検査 です。
ただし、これには全身麻酔が必要で、体への負担や費用(10万円以上かかることも)が大きいため、 年齢や体力、費用のバランスを考え、飼い主さんと獣医師の話し合いで決めなければいけないポイントとなります。
4.薬の開始について
薬を始めるかどうかは、次のような基準で判断されることが多いです。
- 発作が 月に1回以上 起きる
- 発作の時間が長い(数分以上)
- 群発発作(短時間に何度も繰り返す)がある
- 強直間代発作(全身が硬直・けいれんする発作)がある
これらに当てはまる場合は、抗てんかん薬の投与を検討します。
一方、発作が年に数回程度で短時間なら、すぐに薬を始めず「経過観察」を選ぶケースもあります。
5.薬を始めた後の流れ
薬を使い始めたら、定期的に血液検査をして薬の血中濃度をチェックし、副作用がないかを確認します。
また、発作の頻度や様子を記録しておくと、薬の調整にとても役立ちます。
まとめ
- まずは病院で診察 → 一般的な検査で他の病気を除外
- MRIなどの大きな検査は「するかしないか」が分かれる
- 薬は「発作の頻度や重さ」で開始を判断
- 薬を始めたら定期検査と観察が大切
てんかんの治療は「必ずこうする」と決まっているものではなく、犬の状態と飼い主さんの希望に合わせて選択していくものです。
どのようにしていけば良いのか迷うことも多いかと思いますが、一歩一歩、愛犬にあった方法を見つけていきましょう。
👉 次の記事では、実際にミニが病院を受診し、検査・薬を試した体験談をまとめています。
体験談を通して「一般的な流れと、現実の違い」が見えてくるので、ぜひ参考にしてください。